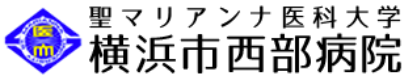聴神経の解剖機能とその障害
聴神経は1つの蝸牛神経(聴覚を担当)と上下あわせて2つの前庭神経(平衡感覚を担当)を併せた総称です。脳幹部の橋と延髄の移行部の外側から出て、すぐ内側にある顔面神経、中間神経とともに内耳道という骨の穴に入り、この穴の行き止まりの部分でさらに分かれ、それぞれ蝸牛と前庭、三半規管に分布します。正確にいえば、聴神経は知覚神経ですので、蝸牛、前庭、三半規管に端を発し、脳幹に入るということになりますが、手術やその他の事項が理解しやすいので便 宜的に上のように述べました。聴神経の機能のうち、前庭神経が担当する平衡感覚について、この神経の障害が急激に起これば「めまい」を感じますが、障害が ゆっくりと進んだ場合には全くといってよいほど症状がでません。それはこの神経系に代償機能が働くからなのです。これに対し、蝸牛神経(聴覚を担当)の障害はその障害速度にかかわらず聴力の低下が起こります。つまり耳が聞こえにくい、聞こえないという症状が出ます。
聴神経腫瘍とは
本態は神経鞘腫という神経周囲の絶縁体の役目をしているシュワン細胞が腫瘍化(正常の制御から逸脱して、かってに増殖すること)したものです。ほとんどの 神経鞘腫は良性で、聴神経腫瘍も例外ではありません。したがって、長年かかってゆっくりと大きくなりますし、転移はありません。聴神経腫瘍の発生母地は蝸 牛神経のこともありますが、大部分は前庭神経にできます。そうすると、腫瘍ができて前庭神経が障害されても、さきに述べたように代償機能が働きますので、 はじめは症状が出ないか、出ても軽いために無視されてしまい、障害が蝸牛神経に及んで、ようやく耳鳴りや聴力の低下に気づきます。この時点でMRIを撮ると、比較的小さい、1cmに満たない大きさの腫瘍が発見されます。小さい腫瘍は大部分が内耳道の中にできます。放置しておきますと、段々大きくなって、内耳道をはみ出し、脳幹の方向に向かって増大します。増大していく場所を小脳橋角部といいます。
さらに大きくなると、橋、延髄という脳幹、また小脳を圧迫してきます。こうなると、聴神経のすぐ内側の顔面神経の機能障害(障害された側の顔の動きが悪くなり、鼻唇溝が浅くなって、眼が閉じにくくなります。また、額にしわを寄せにくくなります。ほとんどの方はこのような症状には気が付きません。)や、舌咽神経、迷走神経、副神経の障害(物が飲み込みにくい、話しづらい、舌が回りにくいといった症状)が加わります。顔面神経のさらに内側の外転神経に障害が及べば物が二重にみえるという複視を伴います。時に舌下神経の麻痺が出て、舌の動きが悪くなります。小脳の症状はふらつく、手が振るえる、物がうまく取れない などの症状です。必ずしも上記の順番で症状が出現するわけではありませんが、おおかたは似通っています。
さらに増大が進むと、脳脊髄液の流通障害が生じ、頭蓋内圧亢進症状(頭痛、嘔気、嘔吐など)が起こります。こうなると命に関わります。
30%ぐらいの患者さんは腫瘍が比較的小さいにもかかわらず、頭蓋内圧亢進症状が出ることがあります。理由は脳脊髄液の中に腫瘍から蛋白質が分泌され、これが脳脊髄液を貯留させる作用があるからと説明されていますが、正確には解明されていません。重要なことは嘔気、嘔吐など明瞭な症状を出さずに慢性的に経 過してしまうことで、慢性的頭蓋内圧亢進は視力の低下を引き起こします。この場合は早急に治療する必要があります。
聴神経腫瘍の治療
1経過観察
聴神経腫瘍が偶然発見されることもありますが、そのような時、MRIで時間を追って大きさを観察することもあります。
2放射線照射
ガンマナイフ治療という特殊な放射線治療で、開頭する必要がないということが最大の利点です。比較的腫瘍が小さい場合、この治療の有効性は明ら かです。つまり腫瘍が縮小しないまでも大きくならないという効果があります。しかし、5〜10%の患者さんはこの治療でも腫瘍が増大してしまいます。どの患者さんに効果があって、どの患者さんにはそうでないのかは明らかではありません。腫瘍が2cm位あっても効果はありますが、副作用が出る可能性もあります。それは、顔面神経麻痺(約7%)、水頭症(約7%)、三叉神経痛などです。
聴力はこれが残存している場合でも40%ぐらいは障害を受けます。最近はガンマナイフ治療の方法論も進歩して、副作用の発現率が低下しつつありますが、困ったことにガンマナイフ治療で起こった顔面神経や三叉神経の障害は時間とともに改善する傾向がみられません。したがって、問題点がないわけではありません。
3外科治療(手術摘出)
腫瘍が大きい場合や、水頭症を併発して治療を急ぐ場合には外科治療以外に方法はありません。具体的方法とその合併症については以下に 記載しましたので参考にして下さい。現状では生命に危険が及ぶことはまずないといってよいほど技術的には進歩しています。余程の出来事(大きな動静脈の損 傷や麻酔の事故など)でもない限り生命の危険性はないといえます。問題はいかに機能を温存できるかという点であります。最新の手術療法を用いても、聴力に関しては、障害された機能を改善させることはできませんし、むしろ悪化してしまいます。ただし、他の脳神経については機能改善が望めます。症状が耳鳴りやごく軽度の聴力低下で、腫瘍が小さい場合には症状を悪化させずに腫瘍摘出することができます。ここで、機能温存と腫瘍の大きさとは極めて深い関係にあることが理解されると思います。一般に次のような温存率が報告されています。
| 腫瘍の最大径 | 2cm以上 | 1〜2cm | 1cm以下 |
|---|---|---|---|
| 顔面神経温存率(形態的) | 72% | 95% | 98% |
| 聴力温存率 | 7% | 30% | 66% |
ここで、顔面神経について、手術直後から機能障害がないのか、あるいは直後は障害があったが時間が経つにつれて機能が改善してきたのかといった問題があります。上記の表は解剖学的に顔面神経が温存された率であり、最終的に顔面神経機能がどのようであったかを表していません。しかしながら、解剖学的に顔面神経が温存された場合、直後は障害があっても、1年以内に約90%の患者さんは一般の方がみて麻痺があるのかないのかわからないぐらいに改善します。したがって、2cm以上の大きい腫瘍でも(72X90=)65% は機能温存が可能ということになります。聴力については腫瘍が小さい場合にのみ温存を期待することができます。私どもの病院の治療成績も上記の表の成績と同等か、むしろ良い結果を得ています。もう一つの問題は腫瘍をどの程度摘出したかという問題です。上記の表は全摘出の結果で、再発は考えなくてよいといえるものです。腫瘍の摘出程度を少なくすればするほど機能温存率は高くなります。このことは当然といえば当然の結果であります。しかし、裏腹に残存した腫瘍がふたたび増大する率も高くなります。具体的にいえば、機能を温存するために腫瘍を残せば、それだけ再発率も高くなります。私どもは腫瘍が大きい場合には、機能温存を優先させて、腫瘍が少し残ってもよいという立場で手術を行っています。現在までこのような方針で再手術を要した患者さんは2人だけですお 1人の患者さんは第1回の手術から13年を経過して再手術を行いました。現在はガンマナイフ治療を併用することも可能です。別のお1人は1回目の手術では 70%ぐらいの摘出率でした。脳幹への癒着の強いことが原因でした。病理学的には悪性ではありませんでしたが増大スピードが速く、1年後には初回手術時の90%ほどの大きさになったので再手術を行い全摘出しました。ただし、若干の失調症状が残存しました。
聴神経腫瘍の手術法
テント下病変手術法の主なものは正中後頭下開頭と外側後頭下開頭です。前者は多くの小脳腫瘍や第四脳室腫瘍などに適用され、バリエーションをもたせて脊髄 空洞症に対する大孔減圧術としても行われます。後者は聴神経腫瘍をはじめとする小脳橋角部腫瘍や椎骨動脈系動脈瘤、三叉神経痛などに用いられ、応用として 片側顔面けいれんの微小血管減圧術があります。
正 中後頭下開頭:腹臥位(うつぶせ)で頭部に固定器を装着後、顎を引くように固定して、項部を伸展させます。外後頭隆起(頸部頭部移行部の骨の隆起)の 3cm上方から第5頸椎棘突起(頚椎の骨の中央後方に突出した部分)のレベルまで正中皮膚切開を行います。軟部組織を正中で切開し、後頭骨から後頭下筋群 を電気メスで剥離して後頭骨を露出する方法が一般的です。当施設では後頭下筋群の上端を正中線に対して直角に交わるように切開し、後頭下筋群の一部を項部 に付着させたまま残すようにしています。こうすると術後の固定性がよく、術野に死腔(余分なスペース)を残しませんので、合併症防止に有効です。開頭法は 一般的開頭法と変わりはなく、ドリルで骨に数箇所の孔を開けたのち、これらを連結するように開頭します。ただし、大孔近辺でのドリル使用は避け、リュエル (骨を削る道具)を用いています。大孔減圧術の場合、後頭下開頭は小さくてよいが、大孔外側部分の骨削除は充分に行います。硬膜は通常Y字 型に切開します。小児では硬膜静脈洞が発達していて、これらを切開することになるので止血処置を準備しておきます。この方法で、小脳の下半分が露出され、大部分の小脳病変に対応できます。必要に応じて第一頚椎の椎弓切除を行い下方の視野を拡大します。第四脳室に到達するためには、正中を剥離し小脳扁桃を左 右に圧排してスペースを作ります。第四脳室の上方に進入するために小脳虫部下半分を切開することもありますが、後遺障害はないと考えて支障ありません。さらに第四脳室を経由して脳幹背側へのアプローチも可能であります。この方法では多くの場合、硬膜閉鎖に際して代用硬膜が必要になります。この場合、脳脊髄 液の漏出がないように配慮します。
外側後頭下開頭
側臥位(横向き)で、手術部位を見やすくするために頭頂部を低くして固定します。後頭下筋群は一層ずつ剥離して、小後頭神経、後 頭動脈を確認しつつ、鋏で切離する。こうすると解剖学的構造を見失うことなく安全です。ドリルで径1-2cm程度の孔をアステリオン(骨の合わさった部分で、解剖学的に重要な目安となる。アステリオンは側頭骨、頭頂骨、後頭骨の合わさった部分)と、乳様突起(耳のすぐ後ろに出っ張った骨)の内側下方に穿 つ。アステリオンの真下には静脈洞があるので注意が必要です。この静脈を損傷すると致命的なことがあります。硬膜はS状 静脈洞側に翻転します。すると、通常は小脳がやや張り出してくるので、へらで軽く小脳を圧排して脳脊髄液の自然流出をはかります。この時点で、吸引などに よるテント下の急激な減圧は避けるべきです。ある程度の減圧を得てから脳槽を開放すると、容易に脳脊髄液が吸引され、小脳を引っ張りやすくなります。正常 解剖では、小脳橋角部に達すると、尾側には下位脳神経(舌咽、迷走、副神経)がみられ、吻側に向かうと順次、聴神経、三叉神経がみえます。また、深部には 外転神経が波打つように観察される。顔面神経は聴神経の内側にあるので見にくいのです。脈絡叢、小脳片葉を手前に引いて、聴神経の下を覗き込むようする と、顔面神経が脳幹から出てくる場所がみえます。小脳橋角部腫瘍(聴神経腫瘍、三叉神経腫瘍、髄膜腫など)では、すぐに腫瘍を確認することができます。腫 瘍摘出は周囲の神経、血管を充分に確認してから取り掛かります。
聴 神経腫瘍では、聴力、顔面神経機能をいかに温存するかが手術の要点であります。腫瘍が大きい場合には、聴力の温存は難しく、小さい場合にも聴力が残るとは 限りません。顔面神経は通常、腫瘍の裏側にあるので、確認することはできません。スペースが狭く、重要な構造物が周囲に存在しますので、腫瘍を一塊にして 摘出することはできません。ごく小さい固まりにして少しずつ摘出します。出血すれば、その都度止血します。止血法は多種類ありますが、よく使用する方法は 双極凝固という、手術用ピンセットの先端のみ電気が流れ、熱を発生させて蛋白質を変性させる方法です。具体的には、前記の理論で、血管が収縮して血液が流 れなくなるのです。したがって、正常の組織に適用すべきものではありません。正常の組織の虚血をきたし、機能喪失を起こす危険があります。摘出操作を進め る段階で、適時、電気刺激により顔面神経の存在部位を確かめつつ手術を行います。ある程度腫瘍のサイズを減じたところで、内耳道の中にある腫瘍を摘出する ために、内耳道後壁の骨をドリルで削ります。
注意点は、
- 周りの組織をドリルの回転に巻き込まないこと
- ドリルを骨に強く押し付けないこと
- 骨の中の空気を含む部位が開放された場合には、脳脊髄液の漏出を防止する処置を行うこと
- 水をかけて過度の熱を発生させないこと
- 手術前に静脈洞の部位を確かめておくこと
などです。この処置により内耳道の中の腫瘍が摘出され、発生源である前庭神経から剥離することができます。そうすると、次第に残りの腫瘍も摘出しやすく なり、また、顔面神経も確認しやすくなります。最終的に腫瘍が全摘出されますと、顔面神経、蝸牛神経、前庭神経の断端がみえます。
術後合併症について
1)開閉頭に伴う合併症
a) 髄液鼻漏
正中後頭下開頭ではこの合併症の可能性はありません。外側後頭下開頭で発生の可能性があります。外側後頭下開頭では、乳様突起と呼ばれる部分に開頭が及ぶことがあります。この骨の部位には乳突蜂巣と呼ぶ蜂の巣のような多数の空洞があり、この部分が開放されることになります。脳には脳脊髄液という無色透明の液 体が脳室や脳表面にあって、別の表現を用いると、脳が水に浮いたような状態になっています。脳の手術を行うと、当然ながら脳の膜を開放します。閉頭時には 膜を縫い合わせてきますが、どうしても水が漏れないようには縫合できません。水周りの処置が難しいのと同じです。乳突蜂巣が開放されると、漏れ出した脳脊 髄液が乳突蜂巣に入り込みます。すると、乳突蜂巣は中耳とつながっていて、中耳は鼻とつながっているので、縫合した脳膜の間から漏れ出した脳脊髄液は鼻か らも漏れ出してしまうことになります。脳脊髄液が漏れ出せば、かわりに空気が脳に入り込みます。これは感染の原因となり、髄膜炎を併発することになり、危険です。術後、髄液鼻漏が発生した場合には、腰椎ドレナージという方法で、一時的に脳脊髄液を腰椎部から体外に排出しておいて(その間、脳脊髄液は脳膜の 間から漏れ出さないという理屈で)、自然に脳膜の隙間が閉鎖されることを期待します。1週を経て自然停止が得られなければ、再手術を行って、脳膜を水漏れのないように閉鎖します。
このような事実がわかっているので、通常、乳突蜂巣が開放された場合には同部を閉鎖するような処置を行います。この目的でフィブリン糊という生体の糊が使用されます。したがって、髄液鼻漏の発生率は低く、私どもも最近10年間に1例経験したのみです。幸い、この方も保存的治療で治癒しています。ただし、5%以上という報告もあるので無視はできません。
b) まれな合併症
開頭時に発生する可能性のある合併症として、静脈洞の損傷、硬膜の損傷、小脳の損傷が挙げられます。静脈洞損傷は時に致命的なことがありますが、術 前に血管に関する情報を充分に得ている現在、発生の可能性は極めて低いし、私どもは経験がありません。硬膜損傷は骨に孔を開けるときに発生する可能性があ ります。特に高齢者では骨と硬膜の付着の程度が強いために発生しやすくなります。ただし、後遺症がでることはありません。なぜなら、閉頭時に硬膜形成を行 うからである。小脳損傷の可能性もありますが、通常考えられません。
2)病変の種類によって異なる危険性
病 変の種類によって危険性とその度合いが異なります。一般論をいえば、脳腫瘍の場合、全摘出が行われないか、あるいはできないと術後に血腫を形成しやすく、再手術を要する確率も高くなります。腫瘍性病変、あるいは出血性病変でなければ再手術の可能性は極めて低いといえます。
3)術後感染
一般的には1%以下の確率であると報告されていますが、実際には非常に低いです。私どもの施設では、テント下病変の手術において、過去10年 間に2例の経験があります。この方々はいずれも8時間に及ぶ長時間の腫瘍摘出術であり、術後1-3か月以上経て、毛嚢炎を契機に感染をきたし、骨を除去することになりましたが、幸いに問題点なく治癒しました。つまり、手術時間が長ければ、それだけ感染の機会も多いのです。
退院の目安とその後の療養について
ほとんどの患者さん(96%)が合併症なく、術後10日ぐらい、長くても2週間で退院されます。長くなる理由としてめまいが挙げられます。どうしても前庭神経に手術操作が加わりますので浮遊感、回転感を残ります。ただし、徐々に改 善しますのでご心配に及びません。時間的には数ヶ月かかる方もありますので、長期的展望をもっていただきたく存じます。
聴力について
聴力は先に述べた程度しか残すことができません。しかも、自然回復はほとんど望めませんので、術前にご理解いただきたい重要な事柄です。
顔面神経機能について
顔面神経について、形態的に残っていれば10ヶ月以内に約90% の患者さんが、注意してみなければ分からない程度に回復します。回復を待っている間に顔面神経麻痺のリハビリテーションを行っていただきます。また、まぶたを閉じることができず、そのために角膜潰瘍を起こすことがありますが、この場合は一時的に上下のまぶたを縫って回復するまでふさいでしまいます。あるいは錘(金)を上のまぶたに埋め込んで瞼が下に下がるようにして角膜を保護します。わたしどもが回復した状態と考えても、患者さんの自覚症状は強く、眼を固く閉じる、口を横に引く等の随意運動を行うと麻痺があることが明瞭にわかります。随意運動を行わなくとも、額にしわを寄せることが難しくなります(この機 能が最も回復しにくいのです)。したがって、患者さんは納得のゆく手術という認識をもつことは不可能と思います。私どもは、いかに顔面神経麻痺を起こさ ず、いかに再発させないように摘出するかを考えなければなりません。患者さんとよく話し合い、透明性のある良質な医療を目指したいと考えています。
顔面神経の再建について
顔面神経が形態的に残っていても機能が回復しないことがあります。その場合、次のような方法で再建を行いますが、何時その判断をするか、つまり、再建したほうが良いのか、あるいはさらに待ったほうが良いのかは術後10ヶ月で行います。なぜなら、10ヶ月以上待つと、顔面筋の萎縮が強くなり、神経機能が回復しても元のように動きにくいのです。再建方法として、1顔面神経と同側の舌下神経をつなぐ方法 2顔面神経と同側の副神経をつなぐ方法 3顔面神経と反対側の顔面神経をつなぐ方法などがあります。いずれも一長一短があります。1の方法(顔面神経 と舌下神経をつなぐ方法)は、舌の萎縮を伴いますが、比較的良い方法と考えています。頚神経わなという舌下神経から分岐した神経を用いると舌の萎縮を防止 できます。ただし、機能回復という点では舌下神経そのものに劣ります。ほとんどの場合、この手術を行うことはありません。なぜなら形態的に顔面神経が残っているからです。過去20年間に 1例のみ顔面神経と頚神経わなの吻合術を適用しました。この方は約半年ほどで回復徴候がみられ、1年後には前額部と眼輪筋を除き術前とほぼ変わりなく顔の筋肉を動かくことができるようになりました。しかしながら気を抜くと顔面神経麻痺が明らかになります。通常は意図せず顔面神経機能が発揮されますが、残念ながら、この患者さんでは意識することが必要になったのです。
不幸にして手術中顔面神経が切れてしまった場合、断端が確認できれば、その場で縫合します。縫合が無理であれば、手術野の採取可能な部位から神経を取り出し(通常、大耳介神経か、大後頭神経)、これを移植します。かつて3例の経験がありますが、いずれも不完全ながら日常生活に支障のない状態に回復しています。2例の患者さんはほとんど麻痺が分からないまでに回復されました。
移植が不可能である場合、たとえば顔面神経が脳幹部からでてくる所で切断されたときなど、回復の望みはありませんので、腫瘍摘出から間を開けずに前記の吻合手術を行います。回復率は先に述べた通りです。