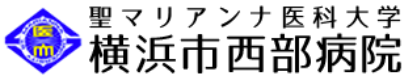髄膜腫は脳を包む膜から発生します。原因はよく判っていませんが、遺伝子が関係するかもしれません。頻度は全脳腫瘍の約27%です。欧米のデータを参考にすると、脳腫瘍の発生頻度は人口10万人あたり1年間に14人ですので、横浜市の人口(約370万人)を考えると、横浜市内で年間に140人の髄膜腫患者が発生することになります。しかし実際にはそれほど多くありません。性質は良性で、時に悪性髄膜腫がみられます。極めてまれには肺に転移したという例もありますが、悪性といっても、肺癌やその他の悪性腫瘍と異なり、急速に大きくなることや、転移することは通常ありません。ただし、再発率は明らかに高率です。最近では、CT、 MRIといった検査が比較的簡便にできますので無症状の髄膜腫もしばしばみられます。治療の対象は基本的に症状があるか、近未来に増大して治療が厄介になることが予測される場合のいずれかです。
治療の方法
- 手術摘出
- ガンマナイフなどの放射線治療
放射線治療を初期治療の方法として用いることもありますが、通常は手術治療の補助と考えています。なぜなら、大きい髄膜腫にはあまり効果がないからです。意図的に取り残した腫瘍や、深部の髄膜腫、超高齢者、手術拒否といった場合に適用を考えます。
手術法の実際
1)一般的開頭法
ごく少数の例外を除き全身麻酔の適用です。頭部の固定は馬蹄形のヘッドレストが使用されることもありますが、通常、三点、ないし四点のピン(釘状の金属)を用いた頭蓋固定装置で頭部を固定します。手術用顕微鏡を使用する機会が多く、微妙な手術操作が多いので、手術中に頭部が動くと危険度が高くなるからです。
頭皮の消毒処置ののち、画像診断に基づく開頭予定部位にしたがい頭皮に切開部位をマーキングします。頭皮は血流が豊富で出血が多いために、止血を目的にエピネフリン入り生理食塩水(血管収縮作用がある)、またはキシロカイン(局所麻酔薬)の皮下注射が行われることもあります。
この事実(血流が多いこと)は逆に頭皮の壊死(腐ること)や縫合不全(縫った皮膚がくっつかないこと)は発生しにくいことになりますが、それでも浅側頭動脈や後頭動脈の走行に留意し、血流が悪くなることを防止するためにこれらを温存するように皮膚弁を作成します。皮膚弁は帽状腱膜下で剥離し、骨膜を残します。骨切開部位のみ骨膜、あるいは筋、筋膜を剥離し、複数個の穿頭(頭蓋骨に径12mm程度の孔を開けること)を行います。
硬膜を剥離子で骨から剥がしておいて、穿頭部を連結するようにクラニオトーム(骨を切る機械)で開頭し、遊離骨弁として骨を除去します。そうすると、髄膜(脳を包む膜)の一つである硬膜という硬く白色の膜が露出されます。単一の穿頭をもとに開頭してもよいのですが、特に高齢者では骨と硬膜との癒着が強いため、硬膜を損傷しやすいので注意が必要です。
骨弁は抗菌剤入り生理食塩水に浸して保存します。硬膜の止血は最小限として、凝固止血による硬膜の収縮を予防します。硬膜切開はくも膜(髄膜の一つで、硬膜直下にある薄い半透明の膜)、脳表を傷つけないように、フックなどでわずかに持ち上げておいて切開を行うとよいと考えています。
硬膜切開法について特にルールはなく、開頭範囲を充分に利用できるように開放します。病変の処置を終了したら、止血を確認後、硬膜を密に縫合します。縫合糸、フィブリンのり(血液成分から作成した接着剤)以外、人工物の使用は避けたほうがよいと思います。
骨弁はチタン製プレートで固定し、以後、軟部組織を吸収糸で順層的に縫合します。表皮はナイロン糸、またはステプラー(一般に商品名ホッチキスとして知られる道具と同様の機械)を用います。いずれにせよ断端が密着していて、わずかにせり上がるぐらいがよく、傷跡が目立ちません。
以上の手術における危険性は低いのですが、硬膜の損傷や、これに伴う脳、あるいは脳表の血管の損傷を考えておく必要があります。発生率は1%と想定されます。手術による感染の発生率は1%に満たないものであり、多くは髄膜炎(かつて脳膜炎といった)で抗生物質により完治することが普通です。
ただし、頭皮やその下部に感染が起こると非常に厄介で、骨を除去する手術、さらに感染が治まったあと、人工骨を入れる手術などが必要になります。一般に感染は術後3-4日で発熱、頭痛、局所の腫れなどの症状で発症します。
したがって術後1週間を経て、これらの症状がない場合には感染の問題をクリアーしたと考えてよいのです。頭皮の感染はその後に発生することもありますが、現在では極めてまれです。
2)髄膜腫摘出術の基本
基本的に髄膜腫は硬膜に付着部位を持ち、脳を圧排して発育し、ときに骨に入り込んで発育します。したがって腫瘍の栄養血管は中硬膜動脈など、外頸動脈の分枝が主であります(頭皮、頭蓋骨、髄膜などへの血液供給は、頚動脈のうち外側の外頸動脈が担当している)。
内頸動脈や椎骨脳底動脈の分枝が栄養血管となることもありますが、多くの場合、副次的です。発育は緩徐で、かなり大きくなるまで症状がないことが一般的です。最近はCTやMRIが行われる機会も増したので、無症候の髄膜腫検出率も増加しました。
治療はガンマナイフやサイバーナイフといった放射線照射法もありますが、基本的に外科的摘出です。この際、腫瘍が入り込んだ骨、付着部位の硬膜、および硬膜内に発育した腫瘍を摘出した場合に全摘出といえます。腫瘍が骨に入り込んでなければ骨は除去しません。
理論的には脳と髄膜腫の間にはくも膜が存在するはずであり、この間で剥離すれば脳を損傷することなく全摘出ができます。実際、小さい髄膜腫は理論通り一塊にして、脳を全く傷つけることなく摘出されます。
しかし、腫瘍が大きく、周囲脳に浮腫(むくみ)を伴う場合など、しばしばくも膜は存在せず、強い癒着がみられます。また、少数ではありますが、悪性髄膜腫では脳への浸潤性発育がみられ、このような場合には摘出操作が難しく、電気凝固器で丹念に止血操作を繰り返しつつ腫瘍を数㎜の小片にして摘出します。
超音波メスも有用で、腫瘍内部をくり抜くようにして腫瘍容積を減少させたのち、周囲脳から剥離をすすめます。元来、髄膜腫は脳組織と性状を異にするので、必ずといってよいほど剥離面を形成することができます。ここで腫瘍表面には比較的太い静脈が張り付いていて、なかには脳実質の拡張した静脈につながっていることがありますので、出血させないように留意します。
一般的な髄膜腫の摘出術の要点は、腫瘍の全貌が観察できるように開頭すること、栄養血管である硬膜動脈を電気凝固しておくこと、腫瘍が付着した硬膜を腫瘍とともに摘出するよう硬膜切開を行うこと、皮質静脈は丁寧に剥離して温存すること、くも膜に沿って剥離操作をすすめ脳表を傷つけぬよう剥離面を作ること、一塊摘出に拘泥しないことであります。硬膜が部分的に欠損するので、同部は代用硬膜(ゴアテックスや骨膜)を用いて閉鎖します。さらに脳脊髄液の漏れ出しを防止する目的でフィブリンのりと呼ばれる血液成分から作った接着剤を使用します。これらの製品での問題点は世界的にみても報告がありません。
3)手術の難しさに影響する因子
摘出の難しさの度合いは、髄膜腫の大きさ、固さ、存在部位、血管の多さに関係します。多くの髄膜腫はかなり大きくなって発見されるので、通常、一塊にして摘出することはできません。なぜなら、そうすることによって、脳を傷つけ、後遺症を残す破目に陥るからです。したがって、小さい固まりに分けて摘出します。固ければ丁寧に切り取る必要があり、大きければ固まりに分ける回数が増えることになり、結局、手術時間が長くなります。
脳の表面に髄膜腫がある場合には、髄膜(脳膜)に付着した部分のすべてが観察できるので、摘出手術は比較的やさしいのです。表面でも、次のような場合は少し厄介です。
静脈洞(硬膜のなかにある大きい静脈)近辺に発生した髄膜腫は静脈洞に入り込んで発育していることがあり、皮質静脈の温存と、静脈洞からの出血制御にも気を配る必要があります。腫瘍が付着した静脈洞壁は摘出するよりも、電気凝固器を用い付着部位を焼灼することによって再発を防止するほうが無難です。静脈洞が腫瘍によって閉塞され、静脈洞に血流がないと判断すれば、静脈洞を含め腫瘍が付着した硬膜はすべて摘出します。
頭蓋底、ことに正中部に腫瘍が発生すると、通常の開頭では、腫瘍に圧迫された脳表しかみえず、全く腫瘍が観察できないこともしばしばあります。また、脳神経や血管を巻き込んで発育することがあり、これらを温存して摘出術を行うことは極めて厄介です。しかも、腫瘍に到達するため、それ相応に脳を引っ張り挙げてスペースをつくる必要があります。あまりに長時間の、あるいは強い力が加われば脳を損傷することになるので、別項に述べる頭蓋底外科手術手技を応用して摘出術を行います。
小片にして摘出することが多いので、最も重要な因子は血管の多さ、つまり、手術中の出血コントロールの問題です。出血が多いと、輸血が必要となり、輸血そのものの問題点も発生します。それ以前に生体に及ぼす侵襲が増大し、各臓器に負担がかかり、術後感染が起こりやすくなります。
また、出血が多ければ、手術部位が血液のために見にくく、判断を鈍らせます。したがって、いかに出血をコントロールするかがキーポイントとなります。先に述べたように、腫瘍を栄養する血管の大部分は腫瘍の硬膜付着部から腫瘍に入り込みます。そこで、まず頭蓋底外科手術手技により、硬膜の外側から腫瘍付着部を観察し、腫瘍の栄養血管を凝固切断します。その後、脳の引っ張り具合をできるだけ少なくするようにして、腫瘍摘出を行います。ときに手術中の手技ではコントロール不能と判断することもあります。極端に栄養血管が発達している場合です。このようなときは、別項にのべる血管内手術手技を適用して、摘出手術を行う直前に栄養血管を塞栓物質で詰めてしまいます。
4)頭蓋底外科手術手技
到達が困難な頭蓋底部に対して、工夫開発された手術法であります。簡単にいうと、通常の開頭法に頭蓋底部の骨切離を追加して、より下方から頭蓋底部を観察する方法です。私どもは腫瘍の存在部位と大きさなどを判断材料として、基本的に4つの方法のうち、1つ、または2つを併用しています。汎用している方法は頭蓋眼窩アプローチ法です。
頭蓋眼窩アプローチ法は、通常の前頭側頭開頭を行ったのち、眼窩上外側の骨を別に切離して眼窩上壁と外側壁を含めて取り出します。こうすると、眼球と視神経が観察されます。蝶形骨小翼と前床突起とよばれる骨組織を取り出すと、より広い術野(手術スペース)が得られ、脳を引っ張ることを少なくして、摘出手術ができます(別紙に詳細が記載してあります)。
次によく使用する到達法が前錐体アプローチです。これも別紙に詳細を示します。
危険性について
1)脳を引っ張るための危険性
脳はある程度の弾力性があって、多少の圧迫に対しては再びもとの状態に復帰します。しかし、引っ張り具合が強いと傷ついてしまいます。そこで引っ張り具合を調節する必要があります。弱い力で引っ張っていても、それが長時間に及べば脳損傷を起こします。このことはちょうど低温火傷に似ています。脳損傷の予防法は、弱い力で、間歇的に脳を引っ張ることであります。このような注意を払っても、術後に脳損傷を起こして出血を伴うことがあり、再手術が必要性なこともあります。その頻度は一般的に5%前後とされますが、私たちの施設では過去10年間に術後再手術を行ったことはありません。一般に再手術は術後6時間以内に行う必要性が生じますので、術後6時間が最初の山といえます。これをクリアーすれば、まず一安心というところです。
例外は出血性素因を持った患者さんです。最近は抗血小板薬、抗凝固薬といった血液を固まりにくくする薬剤を使用している患者さんが比較的多くなってきましたが、そのような患者さんには、あらかじめ内服を中止していただいています。ここで問題にしているのはそのような患者さんではなく、血友病など、先天的に血液が固まりにくい、つまり出血が止まりにくい患者さんのことです。術後6時間以降、24時間ぐらいまで注意が必要です。また、抗がん剤を使用している患者さんにも同じようなことが起こることがあります。
2)髄膜腫周囲の脳や血管損傷の危険性
この問題点を回避するためには腫瘍摘出を行わないことでありますが、それでは手術の目的は達成できません。どうしたらよいでしょうか。基本的には、脳や血管を損傷して、重大な後遺症を残すことが予測されるならば、あえて部分的に腫瘍を残すべきであると考えています。このような状況は腫瘍が脳幹部に強く付着する場合や大きな血管を巻き込んで発育している場合に起こり得ます。残存腫瘍に対しては、経過観察するか、ガンマナイフやサイバーナイフといった放射線照射法の適用を考慮したほうがよいでしょう。
ある程度の脳損傷が予測されても、症状を出さないか、あるいは症状が出現しても回復可能と判断すれば、腫瘍摘出を優先します。なぜなら、根治が望める治療法は手術摘出以外にないからです。
3)髄液漏の危険性
頭蓋底髄膜腫の手術では術後に脳脊髄液が鼻から漏れ出す髄液鼻漏の問題があります。頭蓋内、および脊髄には脳脊髄液という無色透明の液体があって、くも膜と脳表面の間に存在し、正常の状態でおよそ150mlあります。髄膜腫の手術では腫瘍が硬膜(脳の最も外側の膜)に付着しているので、硬膜を含めて摘出します。そうすると、膜の欠損ができますが、通常、代用硬膜を用いて欠損部を補填します。しかし、水まわりの工事が難しいように、どうしても多少の漏れがでてきます。これをいかに防止するかが髄液鼻漏の予防のキーポイントです。骨膜や大腿部の筋膜を使い、さらにフィブリン糊という生体の糊を用い接着させるのですが、さらに脳脊髄液を一時的に体外に排出して、接着部に脳脊髄液が触れない(漏れない)ような方法を併用します。実際には腰椎部のくも膜下腔に細いシリコンチューブを挿入して、無菌的に体外に排出するのです。この間は臥床している必要があり、約4〜7日です。根本的解決法として、時に脳室腹腔シャントという手術が必要になることがあります。
4)水頭症
理由は判然としませんが、頭蓋底外科手術手技を用いて摘出手術を行うような頭蓋底部髄膜腫で、術後約15%の患者さんにシャント手術が必要になることが報告されています。私どもも類似した経験があります。
5)感染の危険性
一般的脳神経外科手術の項に記載しましたので、省略します。
6)輸血についての危険性
現在では輸血をしたための合併症(別紙に詳細が記載してあります)は極めて少ないといえます。例えば、重症の溶血反応は1万回に1回という程度で、かつて問題になった輸血後B型肝炎は24万回に1回とされています。しかし、不具合はゼロではありませんので極力輸血は避けるようにしています。当院では過去15年の経験で、ほとんど輸血を行った記憶がありません。
これに対し、血液から作ったフィブリン糊はほとんどの患者さんに使用しています。この製剤は現在のところ世界的にみても、何かの病気が移ったという報告はありませんのでご安心ください。